そもそも人工知能はどのように発展してきたのか
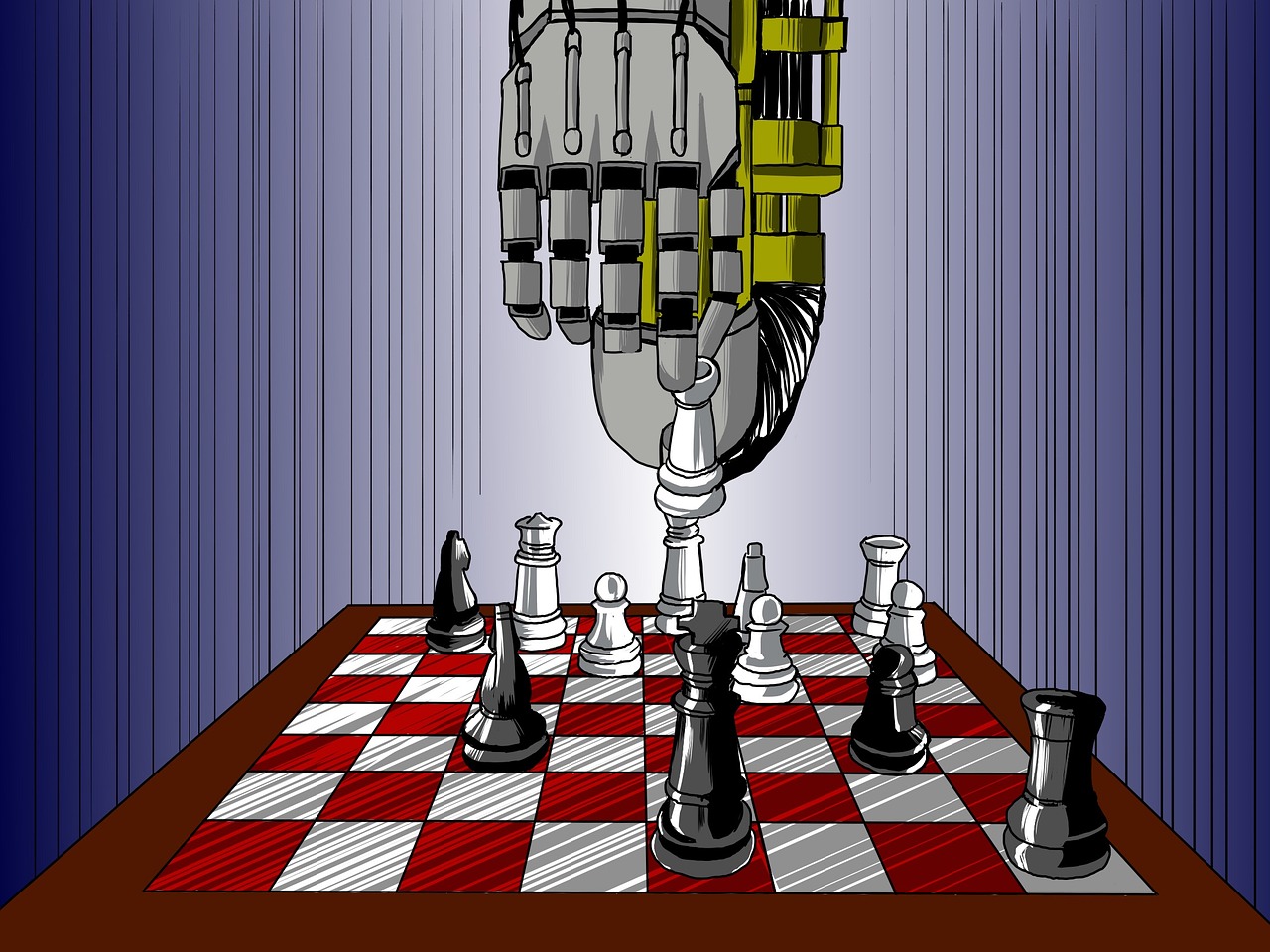
今回は、人工知能がどのように発展してきたかということを振り返り、人間と人工知能の関係を今一度見直していきたいと思います。
人工知能に求められてきた「賢さ」
じつは、「人工知能」には厳密な定義はありません。
人工知能は、研究者により、また時代により、様々な捉え方をされてきました。
Wikipediaには「人工的にコンピュータ上などで人間と同様の知能を実現させようという試み、或いはそのための一連の基礎技術を指す」(Wikipedia)、IT用語辞典e-Wordsでは「人間の脳が行っている知的な作業をコンピュータで模倣したソフトウェアやシステム」(IT用語辞典e-words)という説明があります。
たとえば、パソコンやスマホで、入力した文字を「かな」や「漢字」に変換する機能(かな漢字変換機能)が、人工知能だと言ったら、拍子抜けしてしまうかもしれません。
でも、考え方によっては、パソコンやスマホは人間が覚えきれないような難しい漢字も変換できるし、正しい送り仮名もちゃんと知っています。まさに人間のように、あるいは人間以上に賢い情報処理と言えるでしょう。
コンピュータが普及しはじめた頃には、こうしたことは人が驚くような機能だったわけですから、それが人工知能と呼ばれてもおかしくなかったはずです。
今ではこうした機能は私たちの生活にすっかり溶け込んでしまっていますから、今さら誰もそんなことでは驚きません。
つまり、時代に応じて、賢さの基準が変化してきているわけです。
人工知能の内容、そして応用のされ方は、めまぐるしい広がりを見せています。
ほんの少し前まで、人工知能の話題といえば、迷路を解いたり、チェスを指すといった一種のパズル的なものがほとんどだったのです。
今、人工知能は、かつてのように、単に膨大な数値処理を行うだけのものだけを指すものではなくなっています。
人工知能には次のような「賢さ」が求められています。
- 自律性: 人間が計算手順を指示しなくても、自動手状況に合わせて情報処理を進め、結論を出すことががきる。人間が解き方を教えなくても、自動的に学習してそれを見つけることができる
- 意味性: 単なる数理計算ではなく、データの質や意味のような高度な情報に変えることができる。異なる種類のデータを組み合わせて総合的な判断ができる
- 技巧性: 手当たり次第に計算するのではなく、巧妙な解決法を見つけて解決することができる
- 適応性: 馬鹿の一つ覚えではなく、状況に即した答えを見つけることができる
こうした「賢さ」を得て、人工知能は、大学入試問題を解いたり、写真に写っている被写体を言葉で説明したり、人間と自然な会話をしたり、幅広い領域に応用されるようになっています。
こうしたことは、いずれも、私たち人間が普段の日常の中で、自分の頭で考え、こなしている問題ということができます。
人間が行っている作業を人工知能が代行できるようになるということから、人工知能が人間にとってかわって仕事を奪うのではないかという不安が生まれているのです。
知能は計算式で表すことができる
他の動物がもっていない人間の知能とは、論理的な思考をすることます。
コンピュータであれ、家電製品であれ、人間がつくる道具は、この論理処理の仕組みを反映したものということができます。
たとえば、エレベーターは、
「開ボタンが押され、かつ、ある階に停止している状態であれば、ドアを開く」
というように、複数のルールを総合的に判断して作動します。
コンピュータがこのような論理的思考をできるのは、それが数字と相性がいいからです。
論理的思考は「計算の実行」に置き換えることができます。
ある命題の意味するものが真なら1、偽なら0という数値を割り当てれば、論理は数式になります。
はじめて論理思考を計算式に置き換えたのは、ジョージ・ブールという19世紀イギリスの数学者です。
ブール代数(ブール論理)は、現代のコンピュータ科学分野の基礎的な理論として知られており、次のような対応があります。
| 言葉での表現 | ブール代数での計算 |
|---|---|
| 真である | 1 |
| 偽である | 0 |
| AかつBである | A×B |
| AまたはBである | A+B |
| Aではない | 1-A |
| AとBは値が異なる | (A×(1-B))+((1-A)×B) |
| 「AかつB」ではない | 1-A×B |
エレベーターの例でいえば、
- A: 開ボタンが押されている
- B: ある階に停止している
- C: ドアを開ける
ということになり、AかつBならCということになります。数式で表せば「A×B=C」となり、A、Bが1ならCも1になりますので、Cが実行されるわけです。
「開ボタンが押され、かつ、ある階に停止している状態であれば、ドアを開く」という一見複雑な指示を「A×B=C」という簡単な計算式で表せるわけです。
こうした原理は、電気回路などに用いられていますが、じつは、人間の脳の中でも、電気回路と同じ仕組みが用いられています。神経細胞がお互いに結びつき、信号を送り合う中で、「かつ」「または」といった論理的な変換をしているわけです。
手順を表す「アルゴリズム」
論理的な思考は、ブール代数によって計算式で表すことができるようになりましたが、それを押し進めたものが、人工知能を作動させるための「アルゴリズム」です。
アルゴリズムとは、問題を解くための計算の手順のことです。
問題集の答えをすべて丸暗記したとしても、そこに載っていない問題を解くことはできませんが、アルゴリズムを理解していれば、見た目が変わっでも同じ種類の問題であれば答えを出すことができます。
小学校で教わった「最大公約数」の求め方を覚えていますか?
これは「ユークリッドの互除法」と呼ばれるものですが、そのアルゴリズムは次のようなものになります。
- 2つの数のうち大きい方を「割られる数」、小さい方を「割る数」として、割り算を行い、「余り」を求め、2へ進む
- 「余り」が0なら、割る数を答えとして出力して終了する。それ以外は3に進む
- 「割る数」を「割られる数」、「余り」を「割る数」として、割り算を行い、1に戻る
たとえば、3289と286の最大公約数を求めてみましょう。
- 3289÷286=11 余り143
- 143は0ではないので3に進む
- 286÷143
- 余りは0
- 0なので「143」が答え。終了。
このように、アルゴリズムは曖昧なところなく、具体的な手順を指示しています。
つまり、次に何をすればいいのか、コンピュータでもわかるように作業を指示しているわけです。
さて、人間はこのようなアルゴリズムにのっとって思考していると言えるでしょうか。
人間の場合、「ユークリッドの互除法」のアルゴリズムをもとに答えを出すこともできますが、「これかなと思う数字で試してみる」といったこともできます。
また、「ベートーベンの音楽を聴いて感動する」「猫の写真を見て『猫が写っている』と答える」などといった人間の営為は、アルゴリズムにすることはかなり難しいものになります。
人間の特権ともいえる、こうしたアルゴリズムで書き表すことができない、感性的、直感的な思考ができるようになってきたことが、昨今の人工知能なのです。
人工知能の基礎が揃った20世紀前半
人工知能に「自律性」が求められていると冒頭で書きましたが、自律的な動作をする機械は、それほど目新しいものではありません。
1801年にパリの産業博覧会に織機を出品され、高い評価を得た「ジャカード織機」という機械があります。
これはジャカード織という模様を織るための機械なのですが、この機械が発明される前は、複雑な模様を織る際には大人数で役割分担し、織機の上から必要なタテ糸を持ち上げるという途方もない苦労が必要でした。しかし、ジャガード織機はタテ糸を自動的に上下に開口することができるため、あらゆる模様に対応することが可能になったのです。
さらに、ジャカード織機はパンチカードを用いて制御を行う機械でした。カードを入れ替えることで模様のパターンを簡単に変えられることから、その後、計算機に応用されることになっていくのです。
ジャカード織機のために工程が格段に省力化されたため、当時も、「失業するのではないか」という不安が広がったそうですが、その後10年ほどで、1万1,000台がフランス国内に普及したそうです。
18世紀後半には蒸気機関が登場しましたが、これには、誤差の情報を観測して、機械の動きを補正する自動制御機能(フィードバック)が使われています。
第二次大戦中にはレーダーが発明され、さらにレーダーの機能を高射砲に搭載する研究などが進められました。
しかし、敵機の現在位置めがけて撃っても、着弾する頃には敵機は別な位置に移動します。前に進むとは限らず、旋回することもあり得ますので、高射砲の舵取りは、相手の出方の「先を読む」難しい仕事でした。
このように、機械が生物のように情報を観測し、制御に使えるようにするために提案された学問が「サイバネティクス」です(これは舵手のことをギリシャ語でキュペルネテスということから来た言葉でした)。
同じ頃、シャノンの情報理論が登場し、情報を数学的に定式化すること、つまりあらゆる情報を統一的に扱えることができるようになりました。
たとえば、今のパソコンでは画像や音声、テキストなど様々なデータを扱うことができますが、そもそもこれらはまったく異質のデータです。
シャノンの情報理論は、こうした異なる種類の情報を統一的に扱うための、情報の表現・保存・通信、システムの設計のための基礎理論でした。
このように、20世紀前半に機械を情報化する需要が高まって、理論研究が進み、その後の人工知能の基礎ができあがったのです。
人工知能という言葉が誕生したのは1956年
「人工知能」という言葉が初めて使われたのは、1956年、アメリカのダートマス大学で開かれた研究集会でのことです。
この「ダートマス会議」として科学史に名を残しているこの会議には、草創期の研究者が一堂に会し、1か月もの間、ブレインストーミングが行われました。そこで計算機による複雑な情報処理を意味する言葉として、「人工知能」という言葉が誕生したのです。
この言葉が生まれたことによって、単なる数値計算、機械を制御するためのものだったコンピュータを、人間が行う「思考」というテーマから捉えるという方向性が示されたことになります。
ダートマス会議では、コンピュータ、自然言語処理、ニューラルネットワーク、計算理論、抽象化と創造力など、人工知能に関する様々な側面が話題になり、いずれもその後の研究の大きなテーマになりました。
こうして探索や推論といった人工知能の基本的なコンセプトが提示され、1960年代にになると、実際的な問題への応用が模索されはじめます。
おりしも当時は冷戦という政治状況にあり、そのもとで科学技術が競争の対象となっていました。豊富な研究資金が投入され、人間の視覚と脳の機能をモデル化し、爆発的なニューラルネットブームを巻き起こした「パーセプトロン」、人間と対話できる自然言語処理プログラムELIZA(イライザ)なども生まれ、話題になりました(ELIZAが人間らしさを測るチューリングテストで話題になったことについては、「人間らしさの追求から生まれたチャットボット技術」という記事で紹介しています)。
しかし、当時の研究は、パズルやゲーム、定理の証明など、あくまでも人工的につくられた実験室内の世界での問題を扱ったものであり、現実世界の問題を解決するための応用が始まったのは60年代の後半のことです。
まず、人間の専門家の意思決定能力をエミュレートする「エキスパートシステム」が登場しました。
これは推論エンジンと知識ベースから成り立っているもので、収集した事実や規則などをもとに推論を行い結論を導きます。「地球は丸い」「月は地球の衛星」といった宣言的知識、「赤信号では止まる」「雨が降ったらワイパーを動かす」といった手続き的知識が知識ベースに蓄積されています。
これにより、特定分野においては専門家のように正確な答えを出すことができるようになります。
たとえば、
- DENDRAL: 有機化合物の構造を推定する(スタンフォード大)
- MYCIN: 患者の症状について問答することにより血液中のバクテリアを推定する(スタンフォード大)
- Stanford Cart: 室内環境自律移動ロボット。最初は白線に沿って移動するだけでしたが、進化して、散らかった室内も移動できるようになりました(スタンフォード大)
- DARPA SUR: 音声認識の基礎的技術(米国国防高等研究計画局音声認識研究計画)
- PROSPECTOR: 鉱物資源探索用のエキスパートシステム(米SRI研究所)
- CHAT-80: 日常言語での質問に答えを返す質問応答システム(エジンバラ大)
といったエキスパートシステムが実世界の問題解決のために使われはじめたのです。
冬の時代を超えて、人工知能が今スポットを浴びている理由
エキスパートシステムによって現実世界への応用が始まったとはいえ、人工知能は一般的な産業や日常生活への応用はまだ難しい状態でした。
人工知能というものは、それに対する期待が大きすぎるために、研究成果によって大きすぎる期待が生まれ、その結果、失望につながるというブームと冬の時代が繰り返されるサイクルをたどってきました。
「人工知能はすごいらしい」
「人工知能にはたいしたことはできない」
こういった極端な信頼状況の間を絶えず行ったり来たりしていたのです。
冬の時代には、「人工知能にはこれができない」という後ろ向きの意見が多く語られました。
まず、「人工知能は、積み木を積み上げる作業のような、記号化された問題(トイ・プロブレム)しか解けないから、現実の問題には使えない」と言われました。
たとえば、テーブルの上の置かれたリンゴを認識することができたとしても、人工知能は「半分に切られたリンゴ」「小さなヒメリンゴ」をリンゴと認識することはできませんでした。さらにいえばリンゴが食べ物かどうかということかも判断できません(「食べ物」の知識は無数に存在するため)。
また、「現実の問題を解くためには計算量が膨大になりすぎるため、人工知能では処理しきれない」と言われました。
たとえば将棋は1ゲーム100手ぐらいの長さがありますが、局面ごとの選択肢が10個あるとすると、全体では10の100乗という途方もない局面数になります。これが囲碁になると、手数や選択肢の幅はさらに膨大であり、人間には勝てないだろうと言われました。
こうした冬の時代においても、人工知能の地道な研究は続けられてきましたが、1990年代に再びスポットが当たるようになります。
コンピュータの性能の向上、プラニング技術の進展により1997年にはチェスで人間のチャンピオンに勝利し、画像認識技術も進展して、デジタルカメラが人の顔を認識できるようになりました。
さらにインターネットが巨大なデータをもたらしたことで、大きな技術革新が起こりました。
機械が学習をする上で、データの数は非常に大きな意味をもちます。そこへ、ブログなどの個人生活の文章や写真のデータ、ネットショッピングの顧客行動データ、電車の乗車履歴などの生活行動データなど、多種多様で膨大なビッグデータを人工知能に与えることができるようになったのです。
そして、人工知能を必要とする巨大な企業がインターネットの世界に登場しました。グーグルやフェイスブック、アマゾンといった企業では、マーケティングのために人工知能の力を必要としたのです。こうした企業が積極的な投資を行った結果、自然言語処理技術、ディープラーニング技術が進展することになったのです。
こうして、基礎研究のように扱われてきた人工知能分野に、巨大なビジネスでの実需という強烈なスポットが与えられるようになったのです。
