人間らしさの追求から生まれたチャットボット技術
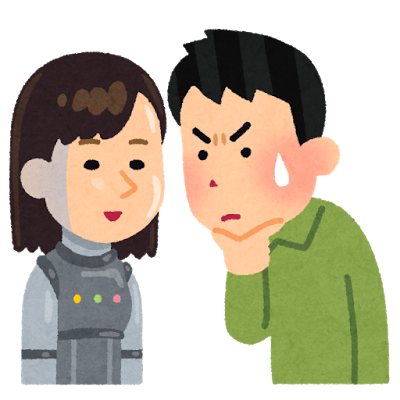
機械の“人間らしさ”を測る「チューリングテスト」
人工知能によって、コンピュータはどれくらい人間に近づいていると言えるでしょうか。
それを測る指標のひとつが、「チューリングテスト」です。
これは、イギリスのサイバネティクス・電子工学研究者だったアラン・チューリング博士が1950年に考案した、機械の知性を判定するテストです。
彼はすでに1941年には機械の知性の概念に取り組んでおり、1947年には「コンピュータの知性」について触れています。
こうして考案されたチューリングテストは、機械が人間と区別できないほど自然に、対話などの知的なふるまいをできるかどうかということを判定します。
チューリングテストでは、一人の人間と機械に対して、審査員が自然言語のテキストで対話を行います。
審査員からは、自分が対話しているのが人間なのか、機械のほうなのかを見ることができないようになっています。
こうしていくつかの質問と回答がなされ、どちらが人間かを審査員が判定するわけです。
どんな内容を質問してもかまいませんし、物語や音楽の感想を聞くというような「意見を求める」ような質問もあります。
人工知能を開発する側の視点からすると、多くの審査員が人間だと思い込んでしまうような機械を作るということになります。
審査員を欺いた機械たち
このテストによって有名になったのが、1966年に発表された「ELIZA」と、1972年に発表された「PARRY」です。
ELIZAをプログラミングしたのはMITのジョセフ・ワイゼンバウム氏です。
当時のコンピュータの性能は現在ほど高くなかったため、できることは限られていました。
そこでワイゼンバウムはルールベースの回答を基本にしたシステムを作りました。
質問の内容をワード分析し、知っているワードがあれば、それについて回答しますが、わからないワードが含まれた質問に対しては、「その質問は重要ですか」などというような、人間が日常生活でよく使う受け流しの返答を返すことで、人間らしさを演出したのです。
例えば「頭が痛い」と言うと、ELIZAは「なぜ、頭が痛いとおっしゃるのですか?」と答えます。
「母は私を嫌っている」と言うと、ELIZAは「あなたの家族で他にあなたを嫌っている人は?」などと返します。
ワイゼンバウムは、これを心理療法のセラピストのパロディだと言っています。
心理療法のセラピストは、もちろん人間ですが、患者の対話の内容に関して知識をほとんど必要としないという特徴があったことを利用したのです。
こうした対話は時として非常にうまくいき、一部の審査員はELIZAの応答を真剣に受け止め、数分間に及んでDOCTORと感情的にやりとりしたと言います。
PARRYもまた、ワイゼンバウムと同様の手法を使って偏執性統合失調症のふるまいを再現したプログラムです。
PARRYの審査では、経験豊富な精神科医が本物の患者とPARRYの両方を精神分析をさせ、別の精神科医33人に会話記録を見せて、どちらが人間でどちらがプログラムかを判別させたのです。
この実験の結果、正しく判別できた精神科医は48%で、これは当てずっぽうで選ぶのとほぼ同様の数字だということになりました。
ELIZAとPARRYは、チューリングテストに合格こそしませんでしたが、それぞれ、30%、50%弱の審査員が人間と判定したことから、テストに合格する機械が近い将来実現されるにちがいないという期待を社会にもたらしました。
審査員のすべての質問に正解を答えることは人間でもできるとは限りませんし、質問によっては、正解がないようなものもあります。
機械の「人間らしいふるまい」を試すチューリングテストにおいては、人間を模倣する技術や話術が重要になるとわかったのです。
チャットボットの技術へ
はじめてチューリングテストに合格した機械は、ロシアのウラジミール・ベセロフ氏とウクライナのユージン・デムチェンコ氏が開発したスーパーコンピュータ「Eugene」です。
Eugeneは「ウクライナに住んでいる13歳の少年」という設定のプログラムで、イギリスのレディング大学で開催されたチューリング博士没後60周年の「Turing Test 2014」というシンポジウム上でテストが実施されましたが、審査員の33%が機械と判別することができなかったため、初の合格者となったのです。
しかし、多くの識者がこの判定結果に対して異論を唱え、物議をかもすことになります。
「設定から、英語が堪能でないという前提がある」
「試験時間が5分だったのは短すぎる」
「実際にインターネットで対話してみたが(Eugeneは期間限定でネット上に公開されました)、会話はつながらなかった」
異論を唱えた中には、他の記事でも紹介している「シンギュラリティ」を予想している人工知能の世界的権威レイ・カールワイル氏もいます。
彼らは、Eugeneはただのチャットボットだと主張したのですが、しかし、そのチャットボットにも、企業の様々なサービスに応用されることによって、社会を変えつつあるインパクトを持っています。
人間らしさの追求から生まれたチャットボット技術 まとめ
人工知能研究には2つの立場があります。
ひとつは、人間の知能そのものをもつ機械を作ろうとする立場。
もうひとつは、人間が知能を使って行うことを機械にさせようとする立場です。
AIという略称はArtificia intelligenceから来ていますが、この「Artificial」には「人工の」という意味の他に「偽りの」という意味もあります。
このことは、現在の人工知能は、あくまでも人間に似せて模造した知能であることを意味しているのではないでしょうか。
